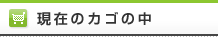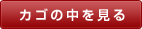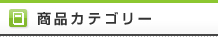内容・概要
コロナ禍で学校の重要性が再認識された一方で、再開後は子どもたちの悲鳴が上がった。
学習指導要領の本格実施やGIGAスクール構想が重なり、大きな混乱と困難が子どもたちと学校を襲っている。
不登校児童生徒や休職教員の急増は、この数年間の教育の変化が大きな要因ではないか。その核にあるものとは。
本書では、目前に迫る学習指導要領改訂を前に、30人余の現場の教員や研究者が、それぞれの立場から、これらの複合的な問題点を明らかにし未来の教育を議論する。
【目次】
はじめに/座談会 学校現場から見える学習指導要領
1、学習指導要領と子どもの学び
学習指導要領の問題点(本田伊克)
学力を「資質・能力」として目標管理する学習指導要領の基本性格(佐貫浩)
観点別評価がもたらす混乱と矛盾(佐貫浩)
【資料】「観点別評価」への教育現場の声
授業のICT化を越える(子安潤)
デジタル化の中のこどもたち(大瀬良篤)
道徳教育の現場から(宮澤弘道)
【コラム】道徳と人権
現実に出会える探究を(山田綾)
2、過大な学習内容と評価の強制
画一的な指導で感性は育たない(国語)(山岡寛樹・大山圭湖)
算数・数学の授業スダンダード化を考える(末定整基)
自然科学をすべての子どものものに(小佐野正樹・関英夫)
何のために歴史を学ぶのか(大八木賢治)
地理教育から見つめる世界(柴田健)
基本的人権と法の支配を軽視した新科目「公共」(菅澤康雄)
英語教育は今 グローバル化の流れの中で(柏村みね子)
子どもの表現は評価のための“プレゼン”ではない(美術)(宮川義弘)
音楽教育をめぐる状況と学習指導要領(小村公次)
人間としての尊厳を保障する技術・職業教育を(坂口謙一)
国の意向が色濃く反映された家庭科(大矢英世)
誰のための、何のための保健体育か (制野俊宏)
【コラム】包括的性教育(池田賢市)
【コラム】「教化」で貫かれた「生命の安全教育」(鶴田敦子)
3、教師の専門性が生きる学習指導要領へ
「ほしいのは、自由とゆとり」(糀谷陽子)
【コラム】「教育DX」の進行と教師の役割(宮澤弘道)
誰のための学校、教育課程、学習指導要領か(寺尾昂浩)
学習指導要領の背景にある新自由主義(児美川孝一郎)
あとがき